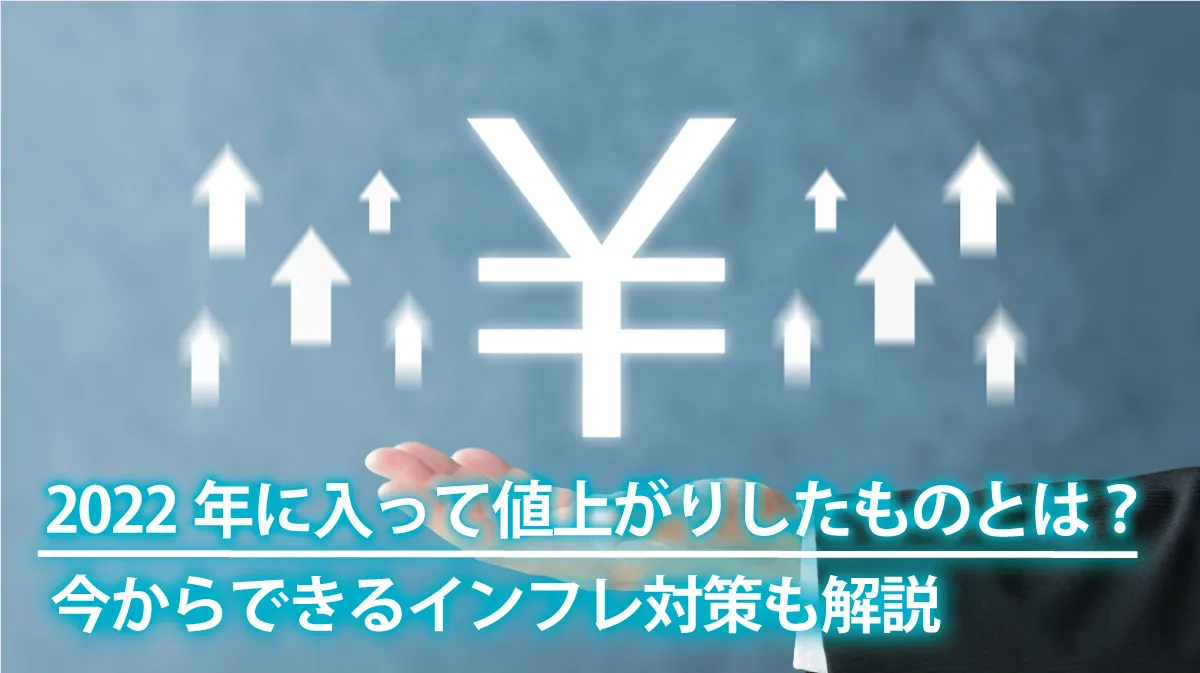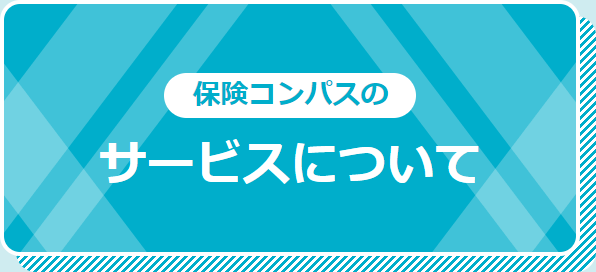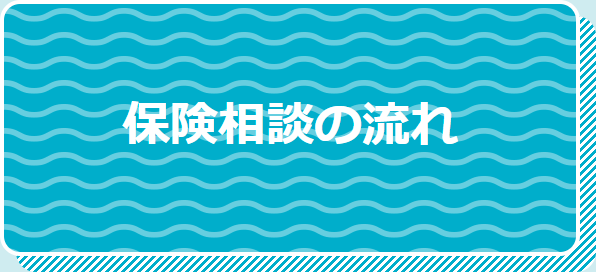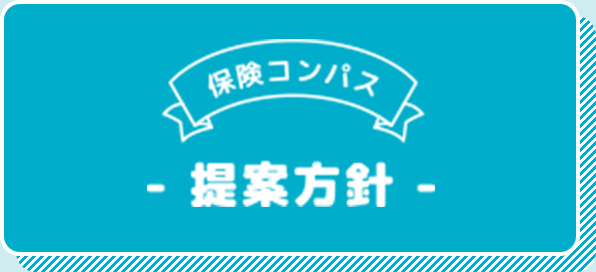2022年には、コロナ禍で停滞していた経済が再び動き出したことにより、世界的に需要が増加しました。それに加え、ロシア・ウクライナ情勢や急激な円安の影響により、多くの商品やサービスが値上げされています。
食料品や日用品、家電など生活に必要不可欠なモノの多くが値上げされたため、家計が苦しくなったという人も多いのではないのでしょうか。
本記事では、2022年に入って値上がりしたものや値上がりの背景、今からできるインフレ対策などをわかりやすく解説します。
2022年は物価が全体的に上昇

まずは、2022年にどれほど物価が上昇したのかを、総務省統計局が発表する消費者物価指数で確認してみましょう。消費者物価指数は、世帯が購入するものやサービスの価格変動を測定するものです。
総務省統計局によると、2022年4〜7月までの消費者物価指数は前年同月比で+2.4〜2.6%でした。また、2022年8〜10月までの前年同月比は+3.0〜3.7%となっています。
価格が変動しやすい生鮮食品を除いた場合も、2022年4〜8月までは+2.1〜2.8%、9〜10月は+3.0〜3.6%となっています。
つまり、2022年は全体的に物価が上昇した年だと言えます。
※出典:総務省統計局「2020年基準消費者物価指数全国2022年(令和4年)10月分」
2022年に入って値上がりしたものとは

続いて、2022年に値上げされた商品の例を項目ごとにみていきましょう。
食品・飲料
2022年は、即席麺や食パン、調味料、乳製品など、多くの食料品が値上げされました。帝国データバンクの調査によると、2022年に値上げされた食品は累計で2万品を超えています。
※参考:株式会社帝国データバンク「食品主要 105 社 価格改定動向調査(12 月)」
このように、さまざまな種類の食料品が値上げされています。値上げされた食品の例は、以下の通りです。
| 食品の種類 | 値上げ例 |
| 即席麺 | ・日清食品 2022年6月1日から即席カップ麺や即席袋麺などのメーカー希望小売価格を5~12%値上げ ・明星食品 2022年6月1日から即席袋麺や即席カップ麺などのメーカー希望小売価格を6〜12%値上げ |
| 食パン・菓子パン・小麦粉 | ・山崎製パン 2022年7月1日から食パンの出荷価格を平均8.7%、菓子パンの出荷価格を平均4.3%値上げ ・敷島製パン 2022年7月1日から商品の出荷価格を約2~9%(平均5.4%)値上げ |
| 小麦粉 | ・日清製粉 2022年6月20日から強力系小麦粉の価格を370円、中力系・薄力系小麦粉を325円、国内産小麦100%小麦粉を385円値上げ※いずれも25kgあたりの税抜価格 ・昭和産業 2022年1月4日から家庭用小麦粉を4〜9%、家庭用プレミックスを約4〜6%、家庭用パスタを約5〜9%値上げ |
| 乳製品 | ・森永乳業 牛乳や飲料、ヨーグルトなど91品の価格を3.6〜10.5%値上げ。改定時期は牛乳・飲料・ヨーグルトが2022年11月1日から、育児用ミルクなどが2022年12月1日から。 ・雪印メグミルク 2022年4月1日よりプロセスチーズ31品の価格を4.5〜10.0%、ナチュラルチーズ4品を4.3〜5.7%値上げ |
| 飲料 | ・大塚食品 2022年4月1日から飲料水(クリスタルガイザー)の価格を10〜20円値上げ ・霧島酒造 2022年9月1日より黒霧島をはじめとした芋焼酎計16銘柄のメーカー希望小売価格を2〜11%程度値上げ |
| 菓子類 | ・カルビー 2022年1月24日からポテトチップスの価格を7〜10%値上げ ・森永製菓 2022年6月1日からアイスクリームの希望小売価格を約6.1〜10.0%値上げ |
| 冷凍食品・レトルト食品 | ・味の素冷凍食品 2022年2月1日から家庭用冷凍食品の価格を約4〜13%、業務用冷凍食品を約3〜8%値上げ ・エスビー食品 2022年9月1日から家庭用即席ルウ製品の希望小売価格を平均9.7%、家庭用レトルト製品を平均5.0%値上げ。 |
また、ほかにも食用油や加工肉、調味料など、さまざまな食品が値上げされました。
外食産業・コンビニ
食料品の値上がりにともない、飲食店やコンビニなども次々と価格の改定が発表されました。2022年に値上げをした企業と商品の例は、以下の通りです。
- マクドナルド
2022年9月30日から約6割の品目の店頭価格10〜30円値上げ - セブン-イレブン
2022年3月2日からサンドイッチの商品価格5〜12%程度値上げ - ファミリーマート
2022年8月23日からファミチキの価格を180円から198円に値上げ - スターバックス
2022年4月13日から定番のコーヒー豆を約90~300円程度、コーヒー・ラテ・フラペチーノなどの定番のビバレッジを約10~55円程度値上げ
日用品・玩具など
ティッシュペーパーやトイレットペーパー、おむつ、おもちゃなど、日ごろの生活で必要性の高い商品も値上げされています。以下は、値上げをした企業・商品の一例です。
- コクヨ
2022年1月1日からノートやファイル、文具などの価格を平均約8%値上げ - 大王製紙
2022年3月22日からティッシュやトイレットペーパー、キッチンタオルなどの価格を15%以上値上げ - 日本製紙
2022年8月1日より印刷用紙や情報用紙の価格を15%以上値上げ - タカラトミー
2022年7月1日からトミカの価格を55円、プラレールの価格を10〜200円程度値上げ
家電製品
冷蔵庫や洗濯機、オーディオ、カメラなどの家電製品も相次いで値上げされました。以下は、2022年に値上げをした企業の一例です。
- アイリスオーヤマ
2022年6月1日から家電製品やホームハウスウェア、収納家具、インテリアなどの価格を10%以上値上げ - Apple
2022年7月1日からiPhoneの価格を2万〜4万円程度値上げ - パナソニック
2022年8月1日から冷蔵庫や食器洗い乾燥機、電子レンジ、炊飯器などの価格を約3〜23%値上げ - ソニー
2022年9月1日からブルーレイディスクレコーダーやデジタル一眼カメラなどの価格を約8%値上げ
水道高熱費
電気料金やガス料金、水道料金も値上げされました。値上げの例は、以下の通りです。
- 東京電力
2022年3月〜9月に電気料金の値上げを実施 - 東京ガス
2022年3〜7月と10〜11月にガス料金を値上げ - 北海道旭川市
2022年7月1日から水道料金を平均で14.9%値上げ
交通・運送など
燃油価格の高騰により、航空機やタクシーなどの運賃が値上げされました。
また、乗用車やトラックなどのタイヤも値上げされています。これは、天然ゴムをはじめとしたタイヤの原材料価格が高騰しているためです。
値上げの事例は、以下の通りです。
- 日本航空
2022年4月15日から2013年4月11日までの運賃を約3〜8%値上げ - 国土交通省
2022年11月14日から東京都特別区や武蔵野市、三鷹市のタクシー運賃を14.24%値上げ - ブリヂストン
2022年4月1日から国内市販用のタイヤやチューブなどの価格を7〜10%値上げ
2022年に物価が上がった背景

2022年に物価が上がった要因の1つは、原油価格の高騰です。新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、一時的に停滞していた世界各国の経済が再び動き出したことでエネルギーの需要が高まり、原油価格が高騰しました。
原油価格の高騰により、ガソリンをはじめとしたエネルギーの価格が上昇したことで、物流にかかるコストが増加しました。また、原油価格はプラスチックの価格にも影響するため、包装資材費も値上がりしています。
原油価格だけでなく、小麦や油脂、食用脂などの原材料価格が高騰したことも物価上昇の主な要因です。特に小麦は、世界的な天候不順による不作により、価格が国際的に値上がりしました。
原油価格や原材料価格の値上がりは、2021年以前からすでに始まっていました。2022年になってから多くのモノやサービスが値上げされたのは「ロシア・ウクライナ情勢」と「急速に進む円安」が大きく影響しています。
ロシアとウクライナは、原油や穀物を生産しています。ロシアがウクライナに侵攻し、これらの供給が滞ったことで、原油価格や原材料価格がさらに高騰しました。
加えて、日本は食料品や原油など多くのモノを海外から輸入しています。急激な円安により、他の国の通貨と比べて円の価値が相対的に下がったことで、海外から輸入しているモノの値段が実質的に値上がりしました。
これら複数の要因が重なった結果、企業努力や経営の合理化だけでは対処が困難になり、2022年には多くの商品が値上げされたのです。
2023年も値上がりは続く?

2023年にもすでに値上げを発表している企業が多数あるため、物価の上昇は今後もしばらく続くと考えられます。
例えば、日清製粉は2023年1月4日から家庭用プレミックス製品(天ぷら粉・お好み焼粉・ホットケーキミックスなど)を約2〜15%値上げする予定です。
また、王子ネピアは2023年1月21日からティッシュやトイレットロールをなどの家庭紙製品の価格を、20%以上値上げします。
物価上昇の要因であるエネルギー価格の高騰や円安がいつまで続くのかは、専門家でさえも予測は困難です。2023年意向も物価上昇が続く可能性はあるため、企業努力に期待するだけでなく、1人ひとりがインフレ対策を考えることが重要でしょう。
今からできるインフレ対策2選

では、個人ができるインフレ対策にはどのような方法があるのでしょうか。今からできるインフレ対策を2つご紹介します。
1.家計を見直す
まずは、家計を見直して無駄な支出を削減できないか検討してみましょう。ひと月当たりの収入と支出を把握していない人は、家計簿を付けることをおすすめします。
支出を見直す際は、保険料や通信費、住居費などの固定費から削ることをおすすめします。
例えば、携帯電話の料金プランを安いものに変更したり、格安SIMに乗り換えたりすると、毎月の通信費を減らせる可能性があります。
また、生命保険の保障内容を見直すと、保険料負担を減らせるかもしれません。特に、子育て世帯の人は、子供が幼いころに生命保険に加入したまま、長いあいだ保障内容を変えていないのであれば、一度見直しをしてみてはいかがでしょうか。
ただし、生活背景や家族構成にあった範囲で見直しをすることが大切です。特に保険の見直しをする際は、保険会社の担当者や保険代理店、ファイナンシャルプランナーに相談することをおすすめします。
2.預貯金以外の資産を持つ
インフレになって物価が上昇すると、現金の価値は相対的に低くなります。例えば、1個100円のリンゴが1個200円に値上がりすると、100円の価値はリンゴ1個分から半分へと下がってしまいます。
預貯金だけで資産を持っていると、インフレが発生したときに保有資産の総額が目減りしてしまうかもしれません。そこで、預貯金以外の資産を持つのも1つの方法です。
例えば、外国の株式に投資をする投資信託で資産を持つ方法があります。投資信託は、さまざまな投資家から集めた資金を1つにまとめて、投資のプロが株式や債券などで運用をする仕組みの金融商品です。
資産の一部を、海外の株式に投資できる投資信託で持っていると、日本の物価が上昇しても、資産全体に与える影響を抑えられます。
投資信託を購入するときは、将来の年金を準備するための「iDeCo」や、毎年一定金額の範囲内で購入した金融商品の運用益に税金がかからなくなる「NISA」といった制度を活用できます。
資産のほとんどが預貯金である人は、こうした制度も活用し、投資信託を始めとした金融商品で資産を保有してはいかがでしょうか。
まとめ

2022年には原油価格と原材料価格の高騰により、多くの商品が値上げされました。特に、食品は2022年のあいだに値上げされた品目が2万品を超えます。また、2023年以降に商品の値上げを発表している企業も多数あります。
将来の予測は専門家でも難しいため、物価の上昇がいつまで続くかはわかりません。家計を見直したり、預貯金以外の資産を保有したりして、個人でもインフレ対策をすることが大切です。
保険コンパスなら、何度でも相談無料です!

宮里 恵
(M・Mプランニング)
保育士、営業事務の仕事を経てファイナンシャルプランナーへ転身。
それから13年間、独身・子育て世代・定年後と、幅広い層から相談をいただいています。特に、主婦FPとして「等身大の目線でのアドバイス」が好評です。
個別相談を主に、マネーセミナーも定期的に行っている他、お金の専門家としてテレビ取材なども受けています。人生100年時代の今、将来のための自助努力、今からできることを一緒に考えていきましょう。