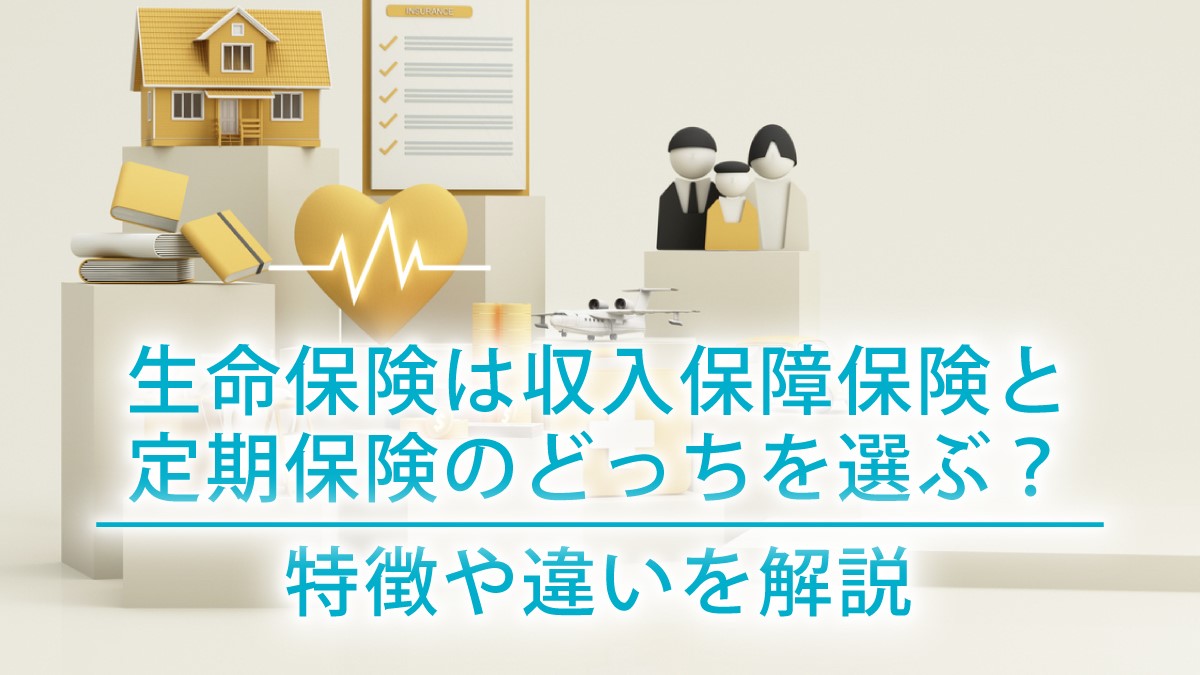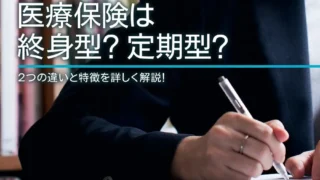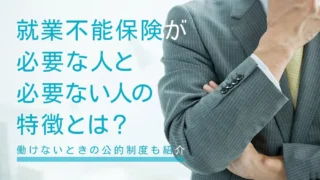収入保障保険と定期保険は、どちらも生命保険(死亡保険)です。被保険者(保険の対象となる人)が亡くなったときや所定の高度障害状態になったときに、保険金が支払われます。
一方で、収入保障保険と定期保険は、保険金の受取方法や保険期間(保障を受けられる期間)など、さまざまな点が異なります。万が一の備えを検討するときは、収入保障保険と定期保険の特徴を理解したうえで、商品を選ぶことが大切です。
今回は、収入保障保険と定期保険の特徴や異なる点、向いている人の例など、選ぶうえで知っておきたいポイントをわかりやすく解説します。
収入保障保険と定期保険の特徴

まずは、収入保障保険と定期保険の主な特徴をみていきましょう。
収入保障保険は保険金を分割で受け取れる
収入保障保険は、死亡・高度障害保険金(以下、死亡保険金)を年金形式で受け取れる保険です。被保険者が亡くなったとき、受取人には毎月のお給料のように保険金が支払われます。
年金形式の場合、保険金が支払われる期間は、保険期間の満了までです。保険期間は「60歳まで」のように被保険者の年齢で決める場合もあれば、「30年間」のように年数を指定して決める場合もあります。
例えば、保険期間が60歳満了、保険金が月額20万円の収入保障保険に加入しているとしましょう。被保険者が40歳で亡くなった場合、給付金の受取総額は「20万円×12か月×(60歳−40歳)=4,800万円」です。
収入保障保険は、保険期間が満了するまでの年数が減ると、保険金の受取総額が変わります。そのため、加入期間の経過にともなって、保険金の受取総額は減少する仕組みです。
保険会社や商品によっては、年金受取だけでなく一括受取も選択できます。ただし一括受取は、年金受取よりも受取総額が少なくなります。
収入保障保険には、2年・5年・10年などの最低保証期間を設定できるのが一般的です。保険期間が満了する間近で被保険者が亡くなったとしても、最低保証期間分の保険金は支払われます。
定期保険は保険金を一括で受け取る
定期保険は、亡くなったときや所定の高度障害常態になったとき、契約時に決めた一定額の保険金が支払われます。通常の定期保険は、保障の開始直後と保険期間が満了する直前のどちらに亡くなっても、保険金の受取額は変わりません。
保険期間は、「歳満了」と「年満了」から選べます。
60歳・65歳・70歳・90歳満了などの年齢で保険期間を設定する「歳満了」と、10年・20年・30年などの年数で保険期間を設定する「年満了」があります。基本的に「歳満了」は更新できませんが、「年満了」は更新することができます。
年満了の定期保険は、保険期間が満期を迎えたときに自動で契約を更新されます。契約内容を変更したうえで、更新をすることも可能です。ただし、更新時点の年齢をもとに保険料は再計算されます。
収入保障保険と定期保険の違い・共通点

収入保障保険と定期保険の主な特徴をまとめると、以下の通りとなります。
| 収入保障保険 | 定期保険 | |
| 保険金の受取方法 | 年金受取また一括受取、あるいはその両方 | 一括受取のみ |
| 保険期間 | 歳満了・年満了 | 年満了・歳満了更新できるのは年満了のみ |
| 保険金の受取総額 | 保険期間の経過とともに減少 | 基本的に一定 |
| 保険料 | 掛け捨て | 掛け捨て |
| 貯蓄機能 | なし | なし |
収入保障保険と定期保険は、どちらも掛け捨て型の保険であり、解約返戻金はありません。その一方で、保険金の受取方法や受取総額、保険期間などに違いがあります。
収入保障保険の保険期間は、契約時に設定した保険期間までの保障なので、基本的に更新はできません。また、歳満了のみを取り扱っており、年満了が選択できない保険会社もあります。
生命保険は収入保障保険と定期保険のどちらを選ぶといいのか

では、万が一に備える場合、収入保障保険と定期保険のどちらを選択するといいのでしょうか。収入保障保険と定期保険のそれぞれが向いている人の特徴をみていきましょう。
収入保障保険が向いている人の例
収入保障保険が向いている人の例は、以下の通りです。
- 保険料負担を抑えたい人
- 見直しの手間を省きたい人
- 遺族が無計画に保険金を使ってしまわないようにしたい人
上記について1つずつ解説します。
保険料負担を抑えたい人
経済的に養っている家族がいる人は、必要な死亡保障額が高い傾向があります。特に、子どもがまだ幼いのであれば、必要保障額が数千万円になるケースも珍しくありません。
保障が開始された当初の保障額が同じである場合、定期保険よりも収入保障保険の方が保険料は安くなります。保険料負担をできるだけ抑えて万が一に手厚く備えたいのであれば、収入保障保険を中心に検討するといいでしょう。
見直しの手間を省きたい人
子育て世帯の場合、家庭を経済的に支える人が亡くなったときの必要保障額を決める際は、子どもが独立するまでの年数も1つの判断基準となります。子どもが成長すると、独立するまでの年数が短くなるため、必要保障額は減っていくのが一般的です。
収入保障保険は、加入している期間の経過とともに保険金の受取総額が減少していくため、子どもの成長にあわせて保障を見直す手間を省きやすいといえます。
遺族が無計画に保険金を使わないようにしたい人
定期保険の場合、3,000万円や5,000万円などの保険金が一括で支払われます。日常生活であまり得ることのない大金を手にした家族が、無計画に保険金を使ってしまうケースも少なくありません。
収入保障保険であれば、保険金は基本的に毎月または毎年といった決まったタイミングで支払われます。そのため、残された家族は、受け取った保険金を計画的に生活費や教育費などに使いやすいといえます。
定期保険が向いている人の例
定期保険が向いている人の例は、以下の通りです。
- 一定期間だけ死亡保障を手厚くしたい人
- 定期的に保障を見直したい人
- 葬儀費用や遺品の整理費用などに備えたい人
一定期間だけ保障が欲しい人
定期保険であれば、保険期間を10年単位の短い期間で設定することも可能です。また短期だけでなく、20年・30年、60歳満了などある程度の期間、決まった保険金額を設定することもできます。
「子どもが大学を卒業するまで」といった一定期間だけ死亡保障を手厚くしたい場合は、定期保険を検討するといいでしょう。また、自営業やフリーランスである人は、事業が軌道に乗るまでのあいだ、定期保険に加入しておく方法もあります。
定期的に保障を見直したい人
更新型の定期保険であれば、ライフプランに応じて保険期間を選択しやすいだけなく、契約を更新すべきか検討する際に保障内容を見直すきっかけもできます。
家族構成や子どもの年齢、住む場所、職業など生活背景の変化にあわせて定期的に保障を見直したい人は、更新型の定期保険を検討するのがいいでしょう。
葬儀費用や遺品の整理費用などに備えたいとき
亡くなったときは、葬儀費用や遺品の整理費用、お墓代などでまとまったお金が必要になるのが一般的です。また、残された家族が家事や育児の負担を軽減するために、家事代行やベビーシッター、食事配達などを利用する可能性も考えられます。
残された配偶者が専業主婦(主夫)である場合、希望する条件に合った就職先がなかなか見つからず、長きにわたって世帯収入が減ってしまうかもしれません。
定期保険であれば、まとまった金額の保険金を受け取ることができ、使い道は受け取った人が自由に決められます。そのため、状況に応じて死後の整理資金や生活の建て直し資金として、受け取った保険金を活用しやすいといえます。
定期保険についてはこちらで詳しく解説しています。
収入保障保険と定期保険を組み合わせるのも方法
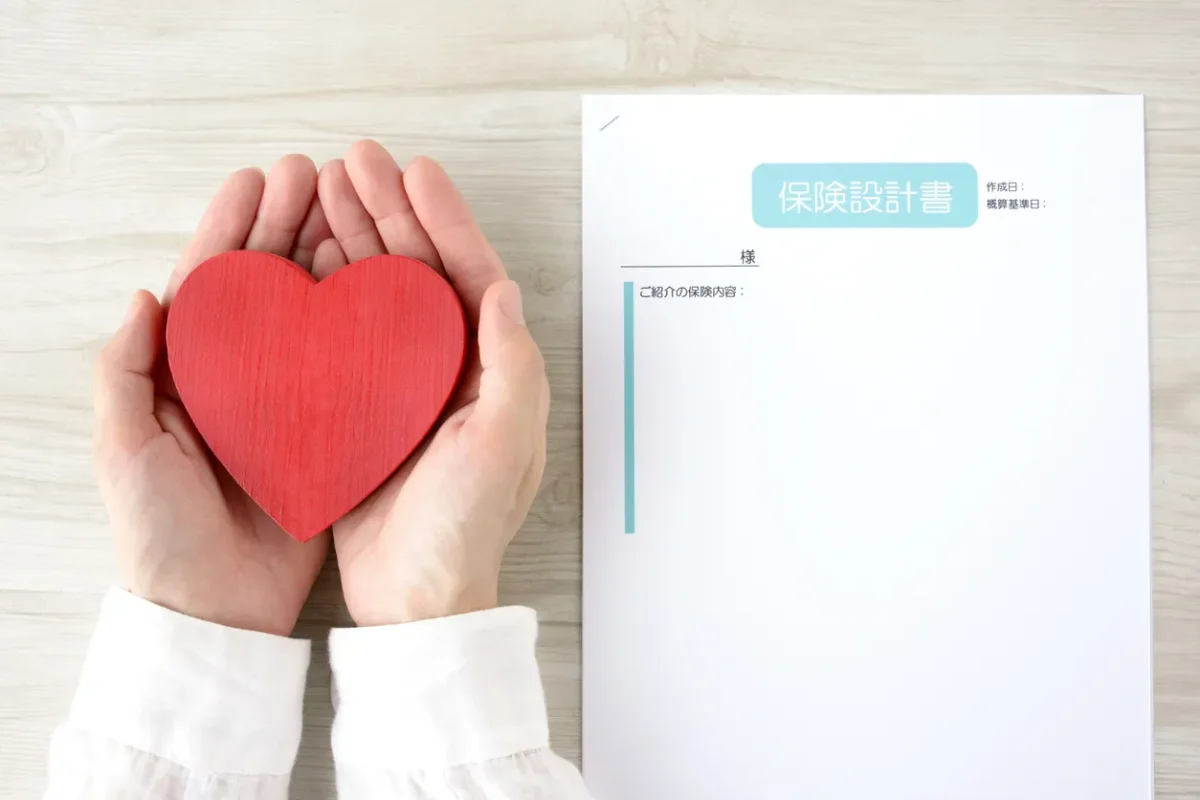
収入保障保険と定期保険のどちらか一方を選ぶのではなく、両者を組み合わせて万が一に備えるのも方法です。
例えば子育て世帯の場合、一家の大黒柱が亡くなったあとの生活費は収入保障保険で備えながら、子どもが独立するまでは定期保険に加入して保障を手厚くする方法があります。
また、死後の整理資金や生活の建て直し資金を定期保険で、残された家族の生活費や教育費を収入保障保険で備えるという選択肢もあります。
万が一の事態に対する備え方は、家族構成や今後のライフプラン、遺族が受け取れる年金(遺族年金)など、さまざまな要素を考慮して決めなければなりません。
死亡保障を検討する際は、保険代理店やファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談するといいでしょう。
収入保障保険とその他の生命保険の違い

生命保険には、収入保障保険や定期保険の他にも「終身保険」や「就業不能保険」などさまざまな種類があります。ここでは、終身保険や就業不能保険が、収入保障保険とどのように異なっているのかを解説します。
終身保険と収入保障保険の違い
終身保険は、一生涯にわたって死亡や所定の高度障害状態に備えられる保険です。収入保障保険の保険期間は一定であるのに対し、終身保険は途中で解約をしない限り、保障が一生涯続きます。
人は年齢を重ねるほど死亡リスクは上がりますが、その一方で病気やケガでいつ亡くなるのかもわかりません。そこで、葬儀費用や遺品の整理費用、お墓代などは、一生涯にわたって備えられる終身保険で準備するのも1つの方法です。
また、掛け捨て型である収入保障保険とは異なり、終身保険には貯蓄機能があり、途中で解約をすると解約返戻金を受け取れます。
亡くなる前に、老後の生活資金や子ども・孫への援助資金などが必要になったときは、終身保険を解約して解約返戻金を受け取ることも可能です。
一方で貯蓄機能がある分、終身保険の保険料は割高です。手厚い死亡保障を準備する場合は、保険料が割安な収入保障保険や定期保険を検討した方がいいでしょう。
終身保険についてはこちらで詳しく解説しています。
就業不能保険と収入保障保険の違い
就業不能保険は、病気やケガで働くことができなくなったときに備えられる保険です。保険期間中に、医師によって所定の就業不能状態と診断された場合に、給付金が支払われます。
保険期間の満了を上限として、就業不能状態が続く限り給付金が支払われるため、働けなくなったときの収入減少や医療費の支払いによる支出の増加をカバーできます。
収入保障保険は死亡や高度障害状態に備える保険であるのに対し、就業不能保険は病気やケガによる就業不能状態に備える保険です。名称は似ていますが、保障内容はまったく異なります。
一方で、保険会社や商品によっては収入保障保険に就業不能特約を付けることで、亡くなったときだけでなく、病気やケガで働けなくなったときにも備えられます。
就業不能保険についてはこちらで詳しく解説しています。
まとめ

収入保障保険と定期保険は、どちらも掛け捨て型の生命保険であり、割安な保険料で手厚い死亡保障を準備できる点は共通しています。
一方で収入保障保険は、保険金を年金形式で受け取れるため、残された家族の生活費を準備する際に活用できます。保険金の受取総額は、保険期間の経過とともに減少する仕組みであるため、定期保険よりも保険料は割安です。
定期保険は、基本的には保険金額が一定です。また、保険期間を10年や20年などに設定でき、商品によっては期間満了時に更新もできます。そのため、短期間だけ保障を手厚くしたり定期的に保障を見直したりしやすい保険といえるでしょう。
また、収入保障保険と定期保険を併用する方法もあります。保険代理店やファイナンシャルプランナーにも相談のうえ、ご自身に合った商品や契約内容を選択し、万が一に備えることが大切です。
保険コンパスなら、何度でも相談無料です!

COMPASS TIMES
編集部
保険やお金に関するコラムはもちろん、身近な病気から最先端医療まで、様々な分野で活躍する名医へのインタビュー記事を集めた「名医の羅針盤」など幅広く特集。
■保険とお金のご相談は保険コンパスへ■
保険コンパスでは、経験豊富なコンサルタントがお客様のご意向をお伺いし、数ある保険の中から最適なプランをご提案いたします。