めまいの原因解明100%を目指して。 患者ファーストでめまいの苦しみから解放する医師
4人に1人は経験したことのある「めまい」は、身近な症状でありながら診療科が多岐にわたるため、 原因を突き止めるのが難しく、患者はもちろん医療関係者も迷うことがあるという。 平穏な暮らしを送ることができず、めまいに苦しんでいる患者を一人でも多く救いたいと、 めまいの原因解明と治療に取り組む北原糺先生に話を伺った。
原因が多岐にわたる「めまい」をあらゆる角度から検査し、 患者の不安を取り除き、完治を目指す。
4人に1人は経験。原因が多岐にわたり時に迷宮入りへ
自分はじっと立ち止まっているのにもかかわらず、ぐるぐる回っているような感覚を覚えたり、 ふわふわしたり、立ちくらみが起こったりと、さまざまな症状が含まれる「めまい」。
医療機関を受診する理由として最も訴えの多い症状の一つだが、 重い症状になると仕事や家事ができず、日常生活に支障が出て悩む人も多いという。 そのめまいの原因解明と治療をライフワークとしているのが、 奈良県立医科大学の教授であり、同大学めまいセンターのセンター長でもある、北原糺先生だ。
「めまいと一口で言いますが、実はその原因が耳にあるとは限りません。 脳腫瘍など、脳の疾患でも起こりますし、うつ病などの精神疾患も原因になりうる。 整形外科や眼科的な原因もありえます。 しかも、老化現象のように、耳も脳も衰えていたとしたら、原因解明が非常に難しくなります」
耳垂れが出ている、鼻水が出ているなど、目に見える症状があるわけではないため、 患者の話をよく聞き、必要と思われる検査をいくつも行い、原因を絞り込んでいく。
耳鼻咽喉科だけでなく、他科とも連携していかなければならないため、 診断までに長い時間がかかったり、原因がわからずじまいだったりと、患者が長期にわたって苦しめられることもあるという。 だが、原因不明と診断されるもののほとんどが、 患者数が一番多いという「良性発作性頭位めまい症(BPPV※1)」であるという統計もある。
「内耳(※2)」にある耳石(※3)が剥がれ落ちてしまい、 三半規管(※4)を撹乱させることによって起こるのがBPPVのメカニズムです。 通常であれば、剥がれ落ちた石は1カ月もすれば体に吸収されてなくなり、症状が治まります。
ところが、剥がれ落ちるのが1回だけでなくて、 次の日も、その次の日も剥がれ続けたらどうなるでしょう。 最初の石は1カ月で消えますが、その後に剥がれた石はまだ残っています。 だから、めまいが1カ月以上続くのです。 すると、医師は『1カ月以上も続くめまいはBPPVではありえない。 原因がわからない』と診断してしまうのです」
画像での診断方法と新薬の開発が今後の課題
耳石は非常に細かい粒であるため、MRIにもCTにも映らず、 剥がれ落ちた耳石が目視できる検査方法はないという。 しかし、対処方法はある。睡眠時に頭を高くすることで、 耳石が落ちるのを防ぐことができれば、めまいは起こらない。 そのためのマットレスを寝具メーカー・昭和西川(株)と共同開発し、昨年販売をスタートさせた。 商品開発のモチベーションとなったのは、患者からの「症状が軽くなりました」というお礼の手紙だった。
「MBT(※5)構想からスタートしたプロジェクトですが、実は、最初はわざわざ専用の寝具を作らなくても、 座布団などで代用できるのではないかと思って患者さんに伝えていました。 しかし『ずれたりしてうまくいかないので、何かいい方法はありませんか』と患者さんから聞かれるようになりました。 さらに、頭を高くして寝ても快適に眠れる寝具がどんなものなのかは、 私にはわかりません。
これは、その道のプロにお任せした方がいいと思いました。 めまいに関する知識と睡眠に関する知識を融合させたことで、 医療の研究成果を患者さんへ具体的な解決法として提示することができる。 論文を書いているだけでは、本当の意味で患者さんのためになっているとは言えませんから」
なぜ耳石は剥がれ落ちてしまうのか、剥がれ落ちない方法はないのか。
「骨粗鬆症などによってカルシウム代謝が悪くなると、耳石も剥がれやすくなります。 年配の女性に多いのはそのためです。 剥がれ落ちないようにする画期的な薬はまだありませんが、 私たちの研究では、漢方など体質改善を促すような何かが、その糸口になるような気がしています」
診療科の枠組みを取りはらっためまいセンター
めまいセンターは耳鼻咽喉科内の機関ではない。 さまざまな診療科からメンバーが集まり、運営会議を実施して問題点を集約・解決するなど、 めまいの症状を持つ患者を中心として、各科が連携して診察や治療を行っていく。
「例えば、ある患者さんが耳鼻咽喉科の領域ではないということがわかったら、 該当する診療科にすばやく連絡がいく。 こういった取り組みは大学病院では珍しく、2016年の設立以降、非常にやりやすくなりました」
さらに、同センターを設立した理由の一つに「わかりやすさ」を挙げる。
「患者さんがめまいの症状を覚えたとしても、何科に行けばいいのかわかりませんよね。 実は医者も同じで、街の診療所などでめまいを診察しても、 医師は『何科を紹介すればいいんだろう?』と迷ってしまうのです。
しかし、めまいセンターという看板を掲げておけば『そこなら間違いない』と迷うことがありません。 あとは、めまいセンターの方で適切な検査をして、 適切な診療科へ割り振ってくれると思ってもらえるのです」
思いがけない結果から、医療が進歩することも。 先入観に惑わされず、原因解明に挑戦し続ける。
短期検査入院による原因解明率は97%を超える
同センターが実施している「短期検査入院」も、 原因が多岐にわたるめまいという症状を、一刻も早く原因解明するために実施している。 これは、めまいに関連する検査を患者が入院している1週間にまとめて実施し、 原因を突き止めることが目的で、退院時には全ての検査結果が出て治療へ移れるという仕組みだ。 原因解明率は97%(2018年4月時点)を超えており、 統計的に原因不明の患者が10%いるということを踏まえると、驚くべき数字である。 しかし、批判もあるという。 「不必要な検査も行っているのではないか」という内容だ。
「確かに、医師が必要と判断した検査だけを実施するのが医療の基本です。 患者さんの話を聞いて、その場でできる簡単な検査をして、そこで診断できればそれでいい。 できなければもっと詳しく検査をして、結果を見て次の手を考える、というのが基本的な診断の仕方です。
しかし、検査というのは大抵の場合、予約制で一つの検査をして異常がなければ、 次の検査は1カ月後になることもざらにあります。 次の月に別の検査をして、異常がない、また次の検査…と繰り返していると、患者さんは疲弊してしまいますし、 精神的にも『私の病気は何なんだろう』と不安になってしまいます」
精神疾患も原因になりうるめまい症患者を、さらに動揺させてしまうのは本末転倒だ。 めまいに関連するありとあらゆる検査を行うことで、患者の不安を解消し、 治療法を示すことで、「平穏な日常生活」に向かって進むことができるのだ。 さらに、メリットの一つに「医師の先入観による検査漏れ」を防ぐことができるという。
先述した通り、原因となる臓器が多岐にわたるめまいでは、 不要だと思った検査が後になって必要だとわかることが多々あるという。 そのことが、診断を長引かせたり、 いくつもの医療機関で同じ検査を何度も受けることになる原因となっている。
思いがけない研究・実験結果が医療の発展へ
めまいの原因の2位にあがる「メニエール病(※6)」は、 実は今も根本的な原因がわかっていない。 ストレスホルモンによって、三半規管にリンパ液がたまることが原因で起こることまではわかっているが、 なぜストレスホルモンによってリンパ液がたまるのか、ストレスは万人が抱えているにもかかわらず、 リンパ液がたまる人とたまらない人がいるのはなぜなのかなど、今もなお謎が多い病気だ。
メニエール病に対する治療である、北原先生が編み出した手術法「内リンパ嚢解放術(※7)」では、 従来の手術法に比べてめまいの抑制と聴力の改善が見られ、2007年には国際的な学会で権威ある賞も受賞している。
「たまったリンパ液を流すために切開するという手術法は昔からあるのですが、 あるとき、その傷のダメージを軽減させる目的でステロイドを留置させました。 それが、実はめまいの抑制や聴力の改善に直接作用しているということがわかり、驚きました」
これには、源泉となるエピソードがある。
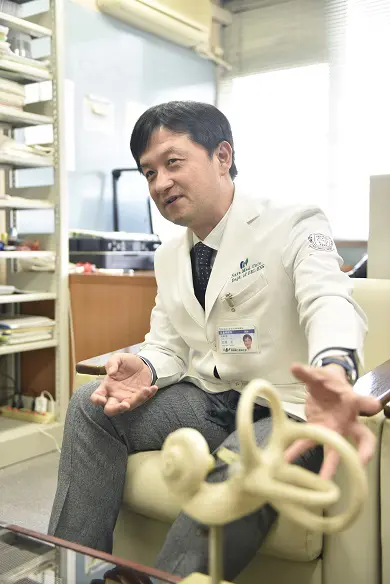
「まだ学生だったころ、ある実験で自分の予想と反する結果が出たことがありました。 自分が手順を間違えたのかと焦りましたが、 指導してくださっていた教授に報告すると『おもしろい』と。 もちろん論拠や、過去の文献による確認作業は必要ですが、 予想と違う結果が出たときになぜそうなったのかを解釈することが重要であると。 そうすることで、今回のような新しい手術法を生み出すことや、 新しい病気の発見などにつながりますし、医学を進歩させることにもつながります」
外科的手術を行ったとしても、切開した傷が閉じてしまい、 再度リンパ液がたまって再発することもあるという。 そのため、根本的な原因解明に向けて、北原先生は闘志を燃やす。
小さなことを気にしないことが一番の予防法
では、めまいの予防法はあるのだろうか。
「原因がさまざまなので一概にはいえませんが、 めまいという症状を大きく捉えると、神経質にならないことでしょうか。 乗り物酔いも三半規管が原因となるのですが、 あれは三半規管が悪いのではなくて、良すぎるのです。 感受性が高いから、揺れを敏感に感じ取って気分が悪くなってしまう。 例えば耳石が剥がれ落ちたとしても、 感じ取ってしまう人もいれば、感じない人もいます。 あとは、平衡感覚を強化する運動です。 だから、気分転換にジョギングすれば、ストレスも解消できて、一石二鳥ですね」
現在の医学では、100%の予防法や治療法が見つかっていない「めまい」。 患者を一人でも多く減らすことと、 画像診断を開発することによって迷う医師を減らすことを目指し、北原先生は歩み続ける。
理解が深まる医療用語解説
(*1)【良性発作性頭位めまい症(BPPV)】
めまいの中で最も患者数の多い。 自分自身や周囲のものが動いたり回転したりしているように感じる。 頭を動かしたことによってカルシウムの粒である耳石が剥がれて三半規管へと入り込み、めまいを起こす。 通常、1カ月ほどで症状は治まり、それ自体は危険な病気ではないが、 運転中に発作が起きたり転倒したりと、事故につながる可能性もある。
(*2)【内耳】
耳を構成している部分の一つ。 蝸牛、前庭、三半規管で成り立っている。
(*3)【耳石】
カルシウムでできた粒状の物質。 三半規管の隣に多数の耳石がくっついた耳石器があり、平衡感覚を保つ役割を担っている。 もろくなってくると剥がれ落ち、頭を動かした際に三半規管へ入り込むことがある。
(*4)【三半規管】
平衡感覚を司る器官。半円形の3つの半規管の総称。 内部にはリンパ液で満たされており、 体が動くことによってリンパ液も動き、上下・前後・左右の動きを感知している。
(*5)【MBT】
Medicine-based Town(医学を基礎とするまちづくり)の略称。 医学を基礎として新産業の創生やまちづくりへと役立てる構想。 医師や医学者と企業との連携により、産業創生、地方創生、少子高齢社会のためのまちづくりを期待されている。
(*6)【メニエール病】
通常、内耳にあるリンパ液は分泌と再吸収が絶えず行われているが、 何らかの原因によりリンパ液がたまってしまい、発生する病気。 日常生活に支障をきたすような重度の回転性めまいや難聴、耳鳴りが起こる場合がある。
(*7)【内リンパ嚢解放術】
メニエール病に対する外科的治療法の一つ。 リンパ液がたまっている内リンパ嚢に穴を開け、 リンパ液を流すことによって正常に戻す。 数年で開けた穴が閉じることもあり、再発の可能性もある。
プロフィール
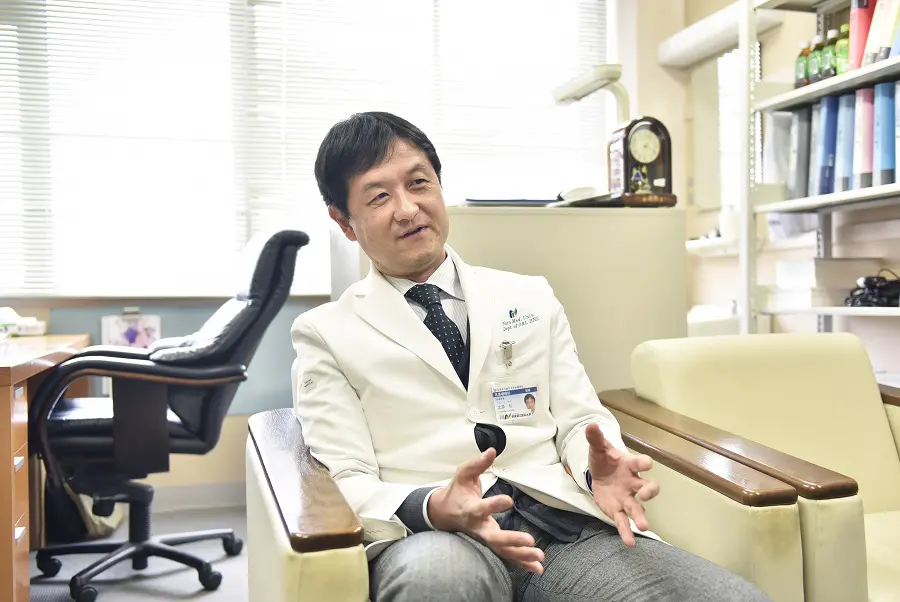
奈良県立医科大学 耳鼻咽喉・頭頸部外科学 教授/めまいセンター長 北原 糺
1997年、大阪大学大学院医学系研究科博士課程修了。 大阪労災病院勤務を経て、大阪大学医学部耳鼻咽喉科、 米ピッツバーグ大学医学部耳鼻咽喉科にて、研究を重ねる。 専門は耳科・神経耳科、めまい平衡医学。 2007年、国際ポリッツァー賞を受賞。 2014年、奈良県立医科大学耳鼻咽喉・頭頸部外科学教授。 2016年、めまいセンター長を兼任する。
取材先
今回はこちらを訪れました!

奈良県立医科大学
〒634-8521 奈良県橿原市四条町840
TEL:0744-22-3051(代表)
http://www.naramed-u.ac.jp/



