がん細胞の遺伝子情報を分析し、
「精密医療」で肺がん治療の現場にレガシーを築く
日本人の死亡原因で最も多い「がん」。
1981年以降、40年以上にわたりトップの座に君臨し続けている。
がん治療が急速な進歩を遂げる現代においても、
「肺がん」は死亡者数・死亡率ともに上昇を続けており、
いまだに難治性の悪性腫瘍の代表格といえる。
かつて不治の病とされた肺がん治療の現場で、
近年、目覚ましい成果を上げているのが薬物療法である。
樋田豊明医師は、薬物による肺がん治療にそのキャリアを捧げてきた。
分子標的療法や免疫療法など、革新的な治療法が続々と生み出される現場に立ち続け、
現在も第一線で治療にあたっている。
肺がんは、近い将来治る病気になるのか。
樋田先生の目を通した「肺がんの過去・現在・未来」をお届けする。
喫煙者数は減少しても、死亡者数は増加する肺がん
1998年に胃がんを抜き死亡者数トップになった肺がん。その後も死亡者数は増え続け、2018年には7万4000人あまりが肺がんで亡くなっている。一見、右肩上がりで増え続けているだけにも見えるが、実はこの20年で肺がんは大きく変わっているという。
肺がんの内容が変わってきているのです。昔は「扁平上皮がん」と呼ばれる喫煙を主な要因とするがんがほとんどでした。しかし近年は喫煙者数の減少とともに、扁平上皮がんもかなり減っています。その代わりに増えてきたのが「腺がん」です。
一昔前は喫煙者が男性に多かったこともあり、肺がんは男性に多く発生していた。しかしこの腺がんは性別に関係なく発生することから、相対的に女性の割合が増えている。
腺がんは肺の一番奥、末梢という部分にできるもので、肺がん全体の6~7割を占めています。発生原因がまだよくわかっておらず、予防が難しいのが現状です。
腺がんの危険因子はまだ判明していないが、発生のメカニズムは明らかにされつつある。発がんのトリガーを引くのが「ドライバー遺伝子」と呼ばれる遺伝子だということだ。
日本人ですと、上皮細胞の増殖を促すEGFR遺伝子(※1)が変異したドライバー遺伝子による腺がんが最も多いです。このドライバー遺伝子は、分かりやすくたとえると膨大な情報量を持つ遺伝子の中についた1カ所の傷により発生します。この傷ががんを増殖させる鍵となるのですが、これは誰でも罹患する可能性があるということを意味しています。
煙草が主要因の扁平上皮がんの場合、複数箇所の遺伝子の変異が積み重なることでがんになることがわかっています。ですから、年齢の高い人に多く発症する傾向がありました。しかしEGFR変異型の腺がんはたった1カ所の変異でがんになるので、若い人でも罹るのです。
さまざまな研究が進められている肺がんだが、なぜ他のがんに比べて死亡率が高いのだろうか。その理由の一つに「転移しやすい」という特徴があるという。
肺は酸素と二酸化炭素を交換する機能を担っていることもあり、血流が豊富なんです。そのため胃がんや大腸がんに比べると局所にとどまる率が非常に低く、転移しやすい。肺がんは初期のうちに見つけて手術すればほぼ治りますが、転移が進行することで治療成績はぐんと下がります。
さらに自覚症状がないこともあり、早期発見が他のがんよりも難しい。この「転移しやすく見つけにくい」特徴が、高い死亡率と密接にかかわっている。
最新の画像診断技術をもってしても、ごく初期の腺がんはほぼ判らないことが問題なのです。定期健診での発見は非常に困難で、がんがある程度大きくなったところで「何かありますね」となったときにはあちこちに転移している。そのようなケースが多いこともあり、なかなか治療成績が上がらないのです。
発見したときにはがんが広がっていて手術できないケースが多い腺がん。この進行がんに対しては内科的治療、とりわけ薬物による治療がメインになる。樋田先生はこの薬物療法の研究に30年以上にわたって身を投じてきた。
世界中の医師たちとともに「不治の病」に挑む

医学部卒業後、2つの病院での研修を経て、愛知県がんセンター病院で医師および研究者としてのキャリアをスタートさせた樋田先生。当時は「不治の病」とされていた肺がん治療の道に進んだ経緯には、どのような理由があったのだろう。
1980年代後半、肺がんの病名告知は死の宣告を意味しました。治療の選択肢もない状態で病名告知はあまりにも残酷であるため、患者さんには「肺にカビがついているだけです」と嘘をつくこともあったと聞きます。
研修中、私は苦しみながら亡くなっていく肺がん患者さんを何人も見てきました。当時多かった扁平上皮がんは気管支や肺の中枢部に発生し、がんにより太い血管が破けて大量に喀血することもありました。そういう悲惨な姿を見る中で、何とか肺がんを治せないか、少しでも効く治療法はないのかという想いを抱くようになり、この道に進もうと決めたのです。
当時、がんの内科療法は、白血病やリンパ腫など血液の分野での研究が先行していた。肺がんの内科治療はまずこの治療法の応用から始まったという。
私を含め、どの医師も完全な手探り状態でした。白血病などに用いられる治療薬などをベースにさまざまなアプローチを試みましたが、どれも肺がんにはあまり効きませんでした。その原因を探るために肺がんの細胞を培養することから始め、肺がん細胞の性質を広く調べるなどするうちに薬が効かなくなる原因や効きにくい原因が少しずつわかってきました。
これらの研究は世界的に注目を集め、1990年代前半にはロンドンの学会にも招かれた。
世界中から集まった医師や研究者を前に拙い英語で発表し、議論を重ねました。どこの国から来ていても「肺がん患者を治したい」という想いは皆同じですから、言葉が通じなくても不思議と通じ合えるんですよね。学会だけでなく海外のワークショップなどにも参加するうちに、少しずつ仲間の輪が世界に広がっていきました。
こうして生まれた海外とのつながりをきっかけに、1994年にはNCI(アメリカ国立がん研究所)で研究員となる。ここでは精密医療(※2)と呼ばれるがん細胞の遺伝子解析をもとにした薬物療法の研究を重ねた。急速な進歩があったのは、分子標的薬の臨床応用が始まってからだという。
私が研修医だったころは、肺がんに罹った患者さんは長くても2年で亡くなっていましたが、この分子標的薬をはじめとした薬物療法の進歩もあって、現在は肺がん全体の5年生存率が30%近くにまで伸びています。
「分子標的療法」とともに、現在の薬物療法の中核を担うのが「免疫療法」だ。
治療成績を劇的に向上させた「分子標的療法」と「免疫療法」
外科治療が難しい進行性の肺がんに対しては、従来、細胞傷害性抗がん剤や放射線による治療が主だった。しかし治療成績はなかなか向上せず、診断後1~2年の生存しか望めない状況が長く続いていた。そこに希望の光が差したのが2000年頃、分子標的薬の臨床応用だった。
肺がんは「小細胞肺がん」「非小細胞肺がん」という2種類の組織型(※3)に大きく分類され、それぞれ性質が大きく異なる。分子標的薬は、後者の非小細胞肺がんの治療に劇的な進歩をもたらした。この治療が出る前と後では治療成績がまったく違うという。
従来の抗がん剤は正常な細胞も攻撃するため、副作用がある上、治療効率の面でもあまりよくありませんでした。この分子標的薬は、患者さんのがん細胞を遺伝子・分子レベルで調べ、その特徴にあわせた薬を用いることで高い効き目を発揮するというものです。がん細胞だけをピンポイントで狙い撃ちすることができるため副作用も比較的少なく、効率的にがんの増殖を抑制することができます。
分子標的薬による治療成績の向上は、特に日本をはじめとしたアジア圏で際立っているという。それはなぜか。
たとえばアメリカの場合、EGFR遺伝子の変異による腺がんは全体の15%程度しかありません。それに対し日本や中国、韓国などのアジア圏では40~50%がEGFR遺伝子の変異によるものです。このEGFR変異がんに分子標的療法が適するということもあり、世界で見てもこの地域の伸びが大きくなっています。
日本人でEGFR変異がんの次に多いのが、ALK陽性肺がん(※4)だ。過去10年間の論文をもとに世界の医療研究者をランキングする「Expertscape」で、このALK陽性肺がんの分野において樋田医師は世界24位にランキングされた。
ALK陽性肺がんは非常に進行が早く、あっという間に転移して悪化します。そのため分子標的薬が登場する前の平均生存期間は1年程度でした。それが「ALK阻害薬」の開発により劇的に改善され、現在では4~5年の生存が可能になっています。私も臨床試験に参加し、ランセット(The Lancet)誌に論文を発表しました。
ただ、分子標的薬が効かないタイプの非小細胞肺がんや小細胞肺がんについては、数十年にわたり薬物治療の進展がなく横ばいの状態が続いていた。その状況を打開したのが「免疫チェックポイント阻害薬」だ。
免疫治療そのものは古くからありますが、近年の研究で、がん細胞が患者さんの持つ免疫の働きにブレーキをかけることが新たにわかってきました。2018年、本庶佑博士がノーベル生理学・医学賞を受賞したことで注目された「免疫チェックポイント阻害薬」は、このがん細胞がかけるブレーキを解除し、免疫細胞の活性化を図るというものです。この治療薬と抗がん剤の併用により、分子標的療法の効果がない非小細胞肺がんや進行型の小細胞肺がんについても一定の割合で長期生存する患者さんが出てきました。余命数カ月という患者さんに投与し、がんが消えてなくなったケースも報告されていますが、そういった効果のある人は今のところ2割程度です。この治療成績を高めるために、現在もさまざまな取り組みが行われています。
分子標的薬は新しい世代へ 〜進化を続ける薬物療法〜

進歩を続ける肺がんの薬物治療。現在はどのような研究が行われているのだろうか。
まず分子標的療法に関していうと、腺がんの半分以上については、要因となる遺伝子が特定されていて、ほぼ出そろってきている状況です。ただ、がん細胞には治療経過とともに自らの構造を変えて薬が効かなくなるような耐性を獲得していくという特徴があります。
抗生物質が第2世代、第3世代と進化してきたように、現在は分子標的薬も同様の進化をする過程にあります。そして、がん細胞に耐性が見つかったらその耐性を解除する薬を開発するという、まさにいたちごっこの様相です。
一方の免疫療法の現在地とは。
実は、免疫チェックポイント阻害薬だけでは十分とはいえません。がん組織周辺にT細胞(※5)を引き寄せる薬を併用することで、本来の効果を発揮できるようになります。そこで現在は、この薬の研究開発が世界中で進められている最中です。今のところ、この免疫チェックポイント阻害薬が有効なのは全体の2割くらいですが、T細胞を引き寄せる薬の開発に成功すれば、この割合が5割、6割、7割になる可能性を秘めています。
樋田先生が肺がん治療センター長を務める中部国際医療センターでは、陽子線治療装置を2023年に導入予定だ。肺がん治療における陽子線治療はどのような役割を担っていくのだろうか。
陽子線治療は粒子をピンポイントでがんに当てて破壊するので効果が非常に高く、患者さんへの負担も少ない。分子標的薬や免疫治療薬でがんを限局的な状態にしてピンポイントで陽子線による局所治療を行うことができるようになれば、さらにがんを抑えられるようになるはずです。
効果的な薬が多くできたからこそ、薬が効かないところに対する局所治療の重要性がより一層増したといえます。今後は陽子線を併用する方向に治療が進んでいくと思いますね。
複雑化・高度化する肺がん治療で、適切な医療を受けるためには
樋田先生が現場に立ち30年。これまでに肺がんの内科療法は着実に進歩してきた。ここからさらにもう一歩、前進するために欠かせないのが検査技術の進歩だ。
医師の目に頼った検査には限界があります。そこで現在はAIを活用した新しい画像検査技術の研究が進んでいます。多くの症例を学習させることで、初期の段階で「これはがんのもとかもしれない」と診断できたら、肺がん治療は大きく前進するでしょう。
革新的な技術が続々と登場し、高度かつ複雑になっている肺がんの診療。医師によって治療成績が左右されることはないのだろうか。
現在の肺がん治療は日進月歩で、世界中で新しい技術が矢継ぎ早に生み出されることで年々複雑なものになっています。呼吸器全般を診ている病院では、肺がん治療の知識や技術の習得が追い付かないこともあるかもしれません。やはり最適な診療を望むのであれば、肺がんを専門に扱う病院にかかるべきだとは思います。
また、肺がんの治療については説明を聞いてもかなり難しく感じられるかもしれません。自身の治療方針に納得がしたい場合は、セカンドオピニオンを聞いてみるのがよいかと思います。
今後、免疫療法のさらなる進歩が見込まれ、進行肺がんについても治療の可能性が見えてきた。希望のある領域といえるのではないか。
そうですね。昔は他の医師に「肺がんの治療やりませんか」とはなかなか言えなかったです。治らない病気でしたからね。今は適した治療法を用いれば、予後が良好になるケースが増えてきていて、非常にやりがいを感じられる現場になっています。
分子標的療法が出てきて、免疫療法が出てきて、治療成績は年々良くなってきています。これから意欲あふれる若い医師や研究者がどんどんこの道を志すようになれば、その進歩はさらに加速するはずです。
理解が深まる医療用語解説
(※1)EGFR遺伝子
EGFR(イージーエフアール)は上皮細胞の増殖を促すタンパク質を生成する遺伝子を指し、ここに変異が発生すると異常なタンパク質が増殖しがん発生につながる。
(※2)精密医療
「個別化医療」「オーダーメイド医療」とも呼ばれる。患者一人ひとりのがん細胞の遺伝子を分析し、最適な治療法を提供するというもので、分子標的療法はここに含まれる。
(※3)肺がんの組織型
がんを調べると、患者によってがん細胞や組織の形に違いが見られる。これらを分類したものを「組織型」と呼ぶ。肺がん全体の1~1.5割が小細胞肺がん、8.5~9割が非小細胞肺がんである。
(※4)ALK陽性肺がん
ALK(アルク)遺伝子とEML4遺伝子が異常に融合した遺伝子を「ALK融合遺伝子」と呼ぶ。この遺伝子が原因となり起こる肺がんがALK陽性肺がんだ。非小細胞肺がんの2~5%がALK陽性肺がんであるといわれ、特に腺がんに多くみられる。
(※5)T細胞
T細胞はTリンパ球とも呼ばれる免疫に関わる細胞の一種で、がん細胞や体の外から侵入した異物を攻撃したり、他の免疫細胞を刺激して抗体産生を活性化させる働きを担っている。
プロフィール
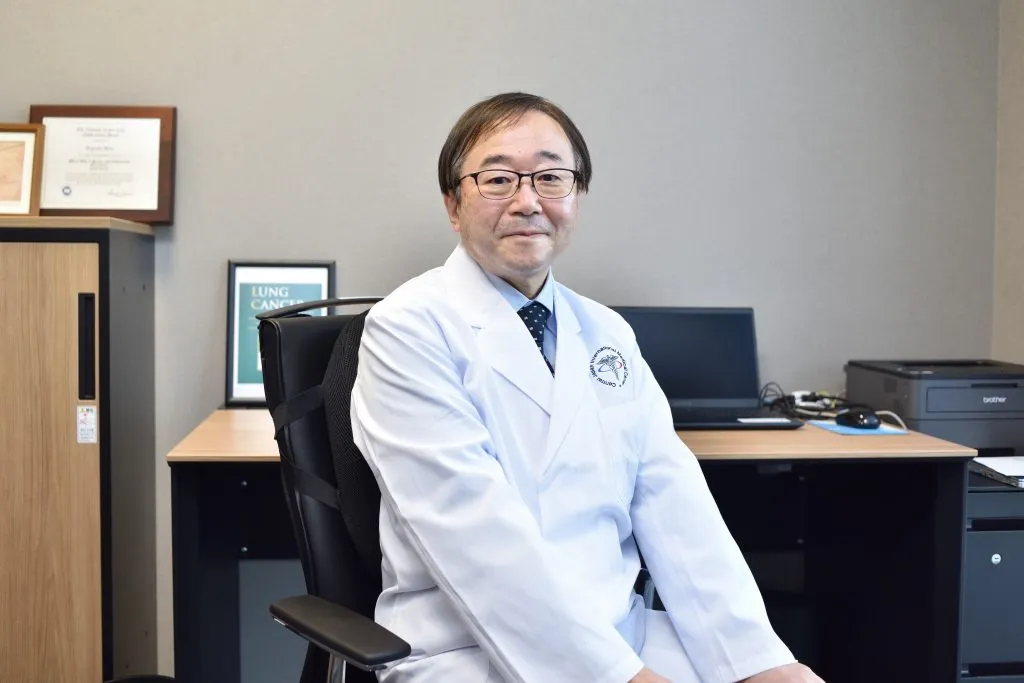
中部国際医療センター
肺がん治療センター長
樋田 豊明(ひだ とよあき)
プロフィール
1980年 名古屋市立大学医学部卒
1982年 遠州総合病院 内科
1986年 愛知県がんセンター病院 内科
1994年 アメリカ国立がん研究所(National Cancer Institute)客員研究員
1996年 愛知県がんセンター病院 呼吸器科医長
2005年 愛知県がんセンター病院 呼吸器内科部長
2006年 名古屋市立大学医学部 臨床教授
2018年 愛知県がんセンター病院 副院長
2022年 中部国際医療センター 肺がん治療センター長
▼今回はこちらを訪れました!

中部国際医療センター
〒505-8510 岐阜県美濃加茂市 健康のまち一丁目1番地
TEL:0574-66-1100
https://cjimc-hp.jp/









