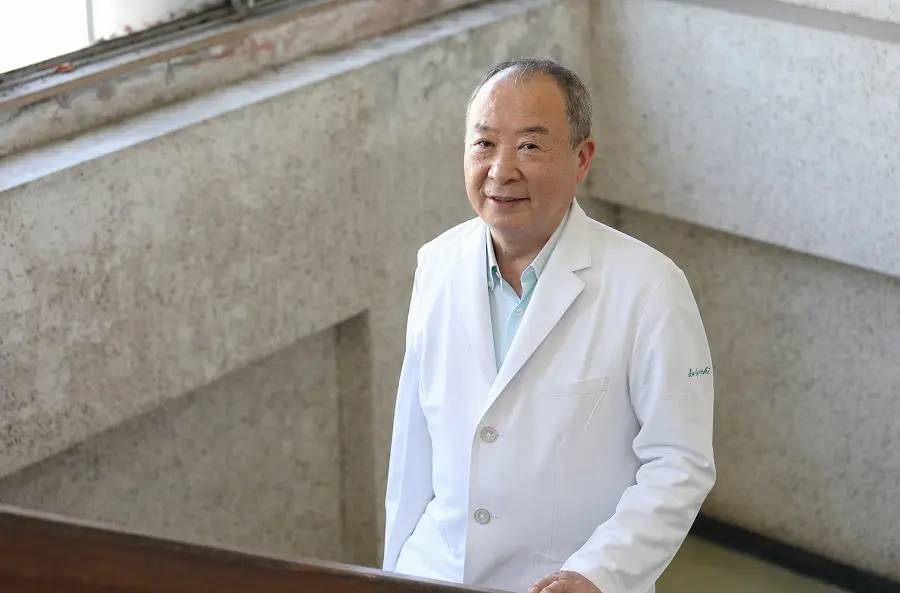大人のアルコール依存症、子どものゲーム依存症… 依存症という病の謎に迫る
「依存症」はれっきとした病気ではあるが、依存症に陥る患者自身に問題があるという認識が根強く存在する。 依存症は患者自身の意思の弱さが原因であり、問題を大きくしているとも思われがちだ。 しかし、依存症は誰もが陥る可能性のある身近な病気であり、 社会全体が依存症への認識を改めなければこの病の根本的解決は望むことができないだろう。 コロナ禍における新しい生活様式が浸透する中で、私たちの生活に静かに忍び寄ってきている病である依存症。 私たちは依存症への認識をどのように改めるべきなのだろうか。 今回は、依存症治療に長年にわたって取り組んでいる樋口進先生にお話を伺った。
「治らない病気」と伝えられ、依存症に立ち向かうことを決意した研修医時代
1979年に東北大学医学部を卒業した樋口先生は、研修医として山形県内の総合病院で働いていた。 ローテーションで精神科の病棟を回っていたとき、入院中のアルコール依存症患者数名を見かけることがあった。 彼らのことに興味を持ち、当時の担当医に「この人たちはどのように治療していくのでしょうか」と尋ねると「しばらく入院してから退院してもらうだけです。この人たちは治りませんから」という答えが返ってきたことに驚いたという。 これは「なぜ積極的に治療をしないのだろう」と、依存症の治療に大いに疑問を抱くきっかけになった出来事となる。 ある時、樋口先生がアルコール依存症患者に興味を持っていることに気づいた担当医は、断酒会(※1)のメンバーを紹介してくれた。
その当時の断酒会は、まだできて間もないころでしたが、会の方々にお会いして話を聞いてみて「こういう方々の治療に携わってみたい」と思ったんですね。 今こうして依存症治療を行っているのは、研修医時代にアルコール依存症の患者さんと、依存症から回復しつつあった断酒会のメンバーにお会いしたことが非常に大きかったと思います。
その後、1982年に国立療養所久里浜病院(現:久里浜医療センター)に移った樋口先生。 ここから、依存症治療との長年にわたる闘いがスタートすることとなる。
「好き」と「依存」の違いとは
趣味などで何かに没頭する人は多いが「好き」と「依存」との境目は非常にあいまいだ。 そのため「好き」を超えて「依存」に陥っていても本人に自覚は芽生えにくい。 どのような状態になれば「依存」と言えるのだろうか。
依存症は、まず快感やワクワク感を求めるという行動が出発点となり陥る病気です。 それらを追い求めるがために行動が行き過ぎてしまったことで、明確な問題が起きている状況は「依存」といえるでしょう。 たとえば、アルコール依存の場合、肝臓に障害が出るので健康問題が明確になりますよね。 また暴言・暴力といった家族の中でのトラブルや借金などの経済的な問題も場合によっては出てくるでしょう。 治療にあたって診断基準はありますが、これは一般の方には非常に分かりにくいものです。 なので、私はいつも「問題が明確に出てきたら、それは依存症です」と患者さんに伝えています。
依存症はリスクといえるはっきりとした要因が少ない病である。 ただ、注意欠如・多動性障害※2(以下、ADHD)は全ての依存症のリスク要因になりうるというデータがあるという。 また、アルコールに関していえば、洋の東西問わず絶対的に「お酒に強い人」の方が依存症になりやすい。 日本人の場合は、飲酒して顔が赤くならない遺伝子を持った人は依存症になりやすいが、逆に顔が赤くなる遺伝子を持った人はなりにくいといわれている。 また、性格的には新奇性追求が高い人や、何か問題があることが分かっているもののそれを気にせず突っ走るような性格の人に依存症患者が多い傾向があるのも特徴といえるだろう。
年齢が低いほど怖い依存症の脅威
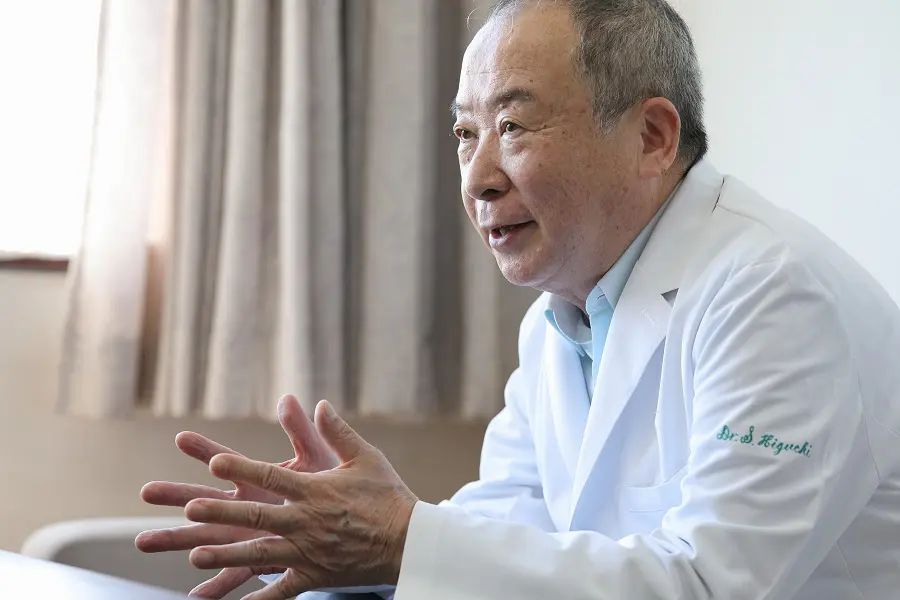
2020年から始まった新型コロナウイルスの感染拡大により、私たちは「新しい生活様式」を余儀なくされた。 ほとんどの地域で全国一斉休校となったこともあり、20年度の内閣府の調査によれば、青少年のインターネットの平均利用時間は19年度が 182.3 分、20 年度が205.4 分と 23.1 分増えた(※)。 それに付随して、オンラインゲームにはまってしまう子どもも多い。 久里浜医療センターに訪れるゲーム依存症患者の症状悪化傾向があると樋口先生は語る。
ゲームにのめり込むことにより、不登校や引きこもりになる、成績が低下する、転校や留年を余儀なくされるなどの問題が出てきます。 また、両親に注意されて暴言・暴力をふるったり、過剰に課金してしまうことが問題になるケースも珍しくありません。 さらに、ゲームに熱中するあまり満足に食事がとれず栄養失調に陥ることや、オンラインゲームは夜中に盛り上がることが多いため、睡眠もままならなくなるケースもあります。 さまざまな健康問題や家族問題、社会問題がゲームの過剰利用にはついてまわるのです。
依存から回復しようとすれば、まず本人が自分に問題があることを認識しなければならない。 ところが、ゲーム依存症に陥る若年層は、ゲーム依存症のままだと自身の将来においてどのような悪影響を及ぼすか想像力が乏しいため治療へのモチベーションが低く、問題を自覚しにくいという課題がある。 また、子どもは「ゲームの時間を減らそう、やめよう」と思っても、それをうまくコントロールする力が大人に比べて弱いため、若年層の依存症治療は困難になりやすい。 特筆すべきは、ゲーム依存症患者には発達障害、特にADHDの子どもたちが多いことだ。 ADHDの子どもは衝動性が高く、自分をコントロールする力が低い。 そのため「ゲームをやめなければ」とは思うものの、ADHD特有の性質がそれを妨げてしまう。 また、オンライン上のバーチャル世界での居心地の良さが依存に拍車をかける要因にもなる。
ゲーム依存症の一番の問題点は、子どもたちの将来に重大なネガティブインパクトがあることです。 そのため、ゲーム依存症の場合、ゲームやインターネットを長時間使用していることよりも、背景にある心の問題や社会への不適応に目を向けることが必要です。 だから、私たちも治療するときにゲームだけに焦点を当てないで、彼らの生活ぶりや、彼らにできることを一緒に考えながら治療していかないといけないと思っています。
※出典:内閣府「令和2年度 青少年のインターネット利用環境実態調査」<https://www8.cao.go.jp/youth/youth-harm/chousa/r02/net-jittai/pdf/2-1-1.pdf>
家庭内暴力に潜むアルコールの影
一部のメディアでは「コロナ禍でアルコール依存症患者が急増している」といった報道が見られるが、国税庁の統計ではコロナ禍以前に比べるとお酒の消費量は減少傾向にあるという。 一部、内科のデータでコロナ禍以前に比べてアルコール性の肝臓障害や膵炎の割合が増えてきているものの、アルコール依存症患者の急増を示すようなデータはほとんどない。
実際、当院の外来を受診されるアルコール依存症の患者さんは、コロナ禍で以前の3分の2くらいに減っています。 減っている理由はアルコール依存が重症化しなくなったのではなく、受診控えしているのかもしれません。 そのあたりの全貌はまだよくわからないですが、アルコール依存症についてはコロナ禍の影響はそんなに大きくなかったのではないかと思います。
久里浜医療センターが2020年6月に断酒会員を対象に行った調査では、緊急事態宣言前後で再飲酒した割合が男性5.9%だったのに対し、女性は10.9%だった。 つまり、女性のほうが再飲酒の割合が高かったのである。 女性の飲酒の理由としては、新しい生活様式で対人関係が希薄になり「寂しい」「孤独を感じる」などが多かったという。 また、樋口先生はコロナ禍のアルコール摂取に関しては依存症以上に「家庭内暴力の増加」が気になっているとも語る。
コロナ禍で家庭内暴力のケースが増えていますが、アルコールがそこに大きく関係しているのではないかと思っています。 どのくらいの割合でアルコールが関係しているかは分からないのですが、やはり外出自粛を推奨される場合は外に行って相談することができないので、家の中にどうしてもこもってしまいますよね。 家庭内にいることで暴力が増え、アルコールが入ればさらに暴力がエスカレートしてしまう可能性がある。 これは、国内だけでなく世界中で懸念されていることです。
対話と環境づくりが依存症治療から“落ちこぼれさせない”ための鍵どのような依存症であっても、もっとも避けなければならないのは治療からのドロップアウトだ。 しかし、ゲーム依存症に罹る子どもの多くが、自身の今の状況や将来への影響を分析する力も弱いため、治療へのモチベーションが低い。 樋口先生が外来診療で一番気を使うことは、いかに彼らに継続的にここに通ってもらうかだという。 そのためにどのような工夫をしているのだろうか。
最初に子どもたちからいろんなお話を聞いた後、心と体の検査を3回ほど行い、その間に彼らと信頼関係を構築します。 彼らも体のあちこちに問題があることを薄々は気がついているので、あまり治療については反抗しません。 また、ご両親と来られている患者さんも、本人だけ別室でカウンセリングを受けてもらいます。 途中で遮られることなく、心ゆくまで話を聞いてもらえることも治療を受ける理由になります。 本人も「自分に何か問題があるな」と心のどこかでは思っているはずです。 問題が全くないと心の底から思っているならば、そもそも病院には来ませんから。
アルコール依存症の治療については、完全に酒類の摂取を断つ「断酒」という方法と、摂取量を減らして治療する「減酒」という方法がある。 とくに近年では減酒による治療が注目を集めており、久里浜医療センターでも2017年4月から減酒外来をスタートしている。 こうした治療法をいち早く取り入れた理由は、アルコール依存症の人をできるだけ治療に向かわせるためだと樋口先生は語る。
アルコール依存症の方は基本的に受診したがりません。 100人のアルコール依存症の方がいたら、受診するのはせいぜい5人ぐらいでしょう。 依存症を抱えている方を治療の場に立たせることは、私たちが長年抱えている課題にもなっています。 なので、減酒という治療法を取り入れることは、治療を受けるひとつのきっかけになってほしいという思いもあります。 減酒は、依存症とまではいえない方や軽度の依存症の場合に当てはまる治療法だと思われがちですが、重度のアルコール依存症でも「絶対にお酒をやめたくない」という患者さんをしっかりつなぎ止めて治療していくためにも有効だといえます。 「まずはお酒を減らしましょう、それがうまくいかなければ断酒も視野に入れましょう」という2段構えの治療は「新アルコール・薬物使用障害の診断治療ガイドライン(※3)」の中にも記載されています。
樋口先生は依存症の治療の場合、できるだけ入院を勧めていると語る。 もちろん、外来での治療ができないわけではないが、依存しているモノやコトから物理的に離れることが可能な入院生活は、精神的にも安定するし身体の状態も改善する。 本人を取り巻く環境を整えるのは、依存症治療には非常に大事なことだという。
依存症であることを隠さない勇気
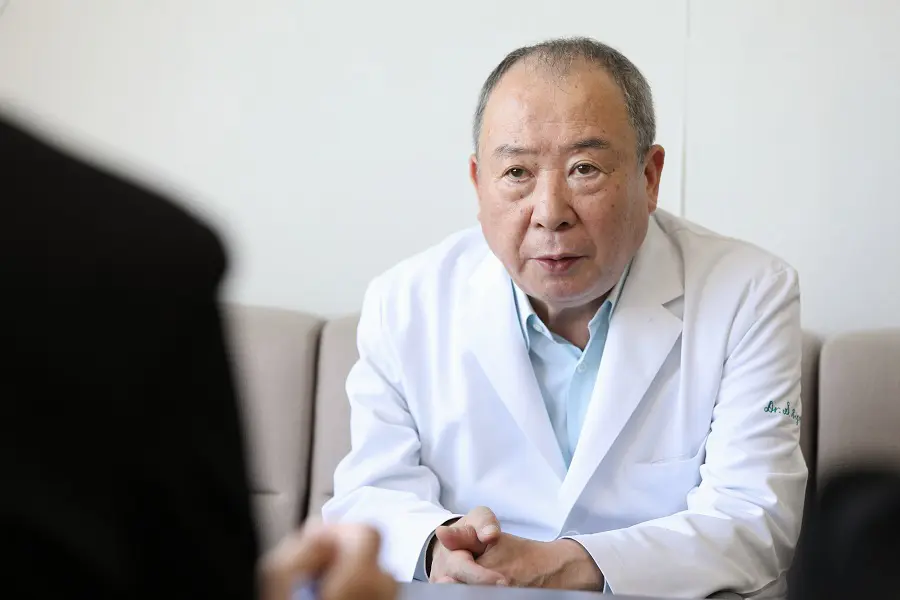
「依存症は完治が難しい病気」というのは事実だ。 たとえば、アルコール依存症の人がお酒を断った生活を何年も続けていても、再び飲酒を始めてしまうとまた依存症に陥ってしまうことは珍しいケースではない。 依存症になる以前のようにお酒をうまく楽しむ生活ができるようになることこそ「回復」と呼べるが、依存症は再発するという特性があるため完治することが非常に難しいと言わざるを得ない。
再発については原因となる脳のメカニズムがあるはずですが、神経科学がこれだけ発達してもそれらしいものがまだ説明できないのが実情です。 再発を回避するには、やはりやめ続けるしかありません。 やめ続けている間はごく普通の生活ができますが、それができる人たちは実はあまり多くないのも事実です。 アルコール、ギャンブル、ゲームといった依存症においても同じことがいえます。
では、依存症患者本人や周りの人たちはどのように依存症と向き合えばよいのか。
依存症は隠しているよりもオープンにしたほうが治療は成功しやすいといえます。 自身の行動が行き過ぎているかもしれないと思ったら、医療機関の受診や精神保健福祉センター(※4)への相談など、外部にヘルプを求めるのが大切だと思います。 たとえばアルコール依存症の方は飲み会に誘わないようにする、といった周囲の気遣いも非常に大事ですが、依存症であることを隠してしまうとこうした周囲のフォローも受けにくい。 昔は「依存症はごく一部の難のある人たちがなるもの」だと誤解されていましたが、さまざまな依存症が少しずつ理解されはじめてきたかなと感じています。 そのため、僕はいつも患者さんには「恥ずかしいから隠したいという気持ちはわかるけれど、治療と割り切ってご自身から周囲の方に配慮してほしいと言うようにしなさい」と伝えています。
WHOを動かした名医は、さらなる高みへ
久里浜医療センターの院長に就任し10年ほど経った今、樋口先生に今後の依存症医療の展望について伺ってみた。
医師となってから今まで40年以上、依存症治療に尽力してきました。 特にゲーム依存症はあまりにも重症な方が多いことに危機感を覚え「研究を進めて治療法を確立するためには、疾病化がどうしても必要だ」とWHOに働きかけて疾病として認めてもらうことにつながりました。 しかし、買い物依存や性依存、食べ物依存などのように、疾病化して治療法を確立していかなければいけないものが今なお多く残っています。 そろそろ院長職は次の世代に譲ろうかと考えていますが、治療や研究の面でもまだ貢献していきたいので、依存症治療の未来を引き続き切り拓いていきたいと思います。
理解が深まる医療用語解説
(※1)断酒会
アルコール依存症患者のための自助組織。お互いに抱えている問題や酒害体験を共有することで、支え合い問題の解決を目指すことを目的としている。
(※2)注意欠如・多動性障害
集中力がない、じっとしていられない、思いつくと行動してしまうといった症状が見られる障害。症状によって「不注意優勢に存在」「多動・衝動優勢に存在」「混合して存在」と分類される。
(※3) 新アルコール・薬物使用障害の診断治療ガイドライン
飲酒量低減という治療選択肢を加え、2018年に公開された診断治療ガイドライン。初期のアルコール依存症患者に焦点をあて、専門医療機関以外でも対応が可能となることを目的として作成された。
(※4) 精神保健福祉センター
各都道府県に設置されている精神保健福祉に関する技術的中核機関。メンタルヘルスについて幅広く相談可能な支援機関として、相談者の自立や社会復帰を支えている。
プロフィール
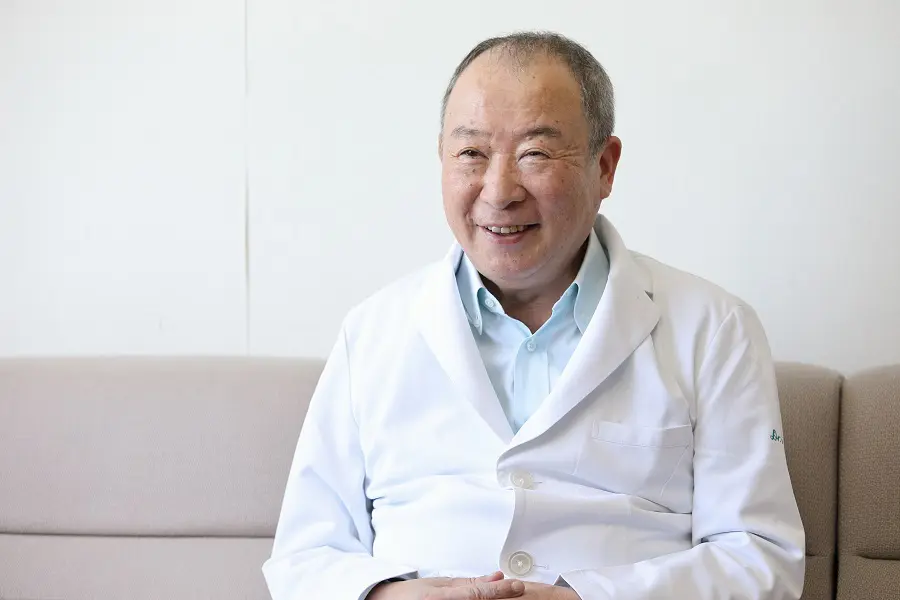
独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター
院長
樋口 進(ひぐち すすむ)
プロフィール
1979年 東北大学医学部 卒業
1982年 慶應義塾大学医学部 助手
1982年 国立療養所久里浜病院 医員
1991年 国立療養所久里浜病院 医長
1997年 国立療養所久里浜病院 臨床研究部長
2000年 国立療養所久里浜病院 副院長
2011年 独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター 院長
インターネット依存症・ギャンブル依存症・アルコール依存症の診療に携わる傍ら、うつ病、パニック障害、統合失調症等の一般精神疾患も幅広く診療している。
▼今回はこちらを訪れました!

独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター
〒239-0841 神奈川県横須賀市野比5-3-1
TEL:046-848-1550
https://kurihama.hosp.go.jp/